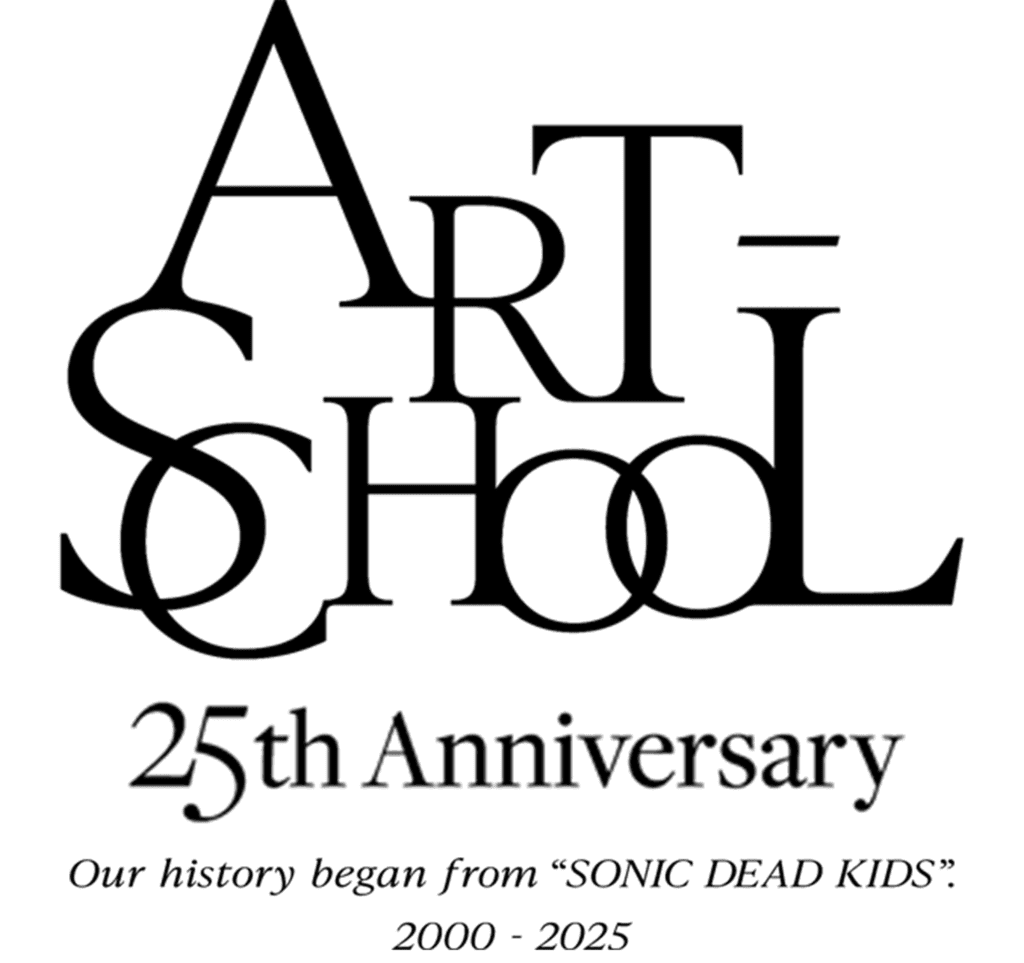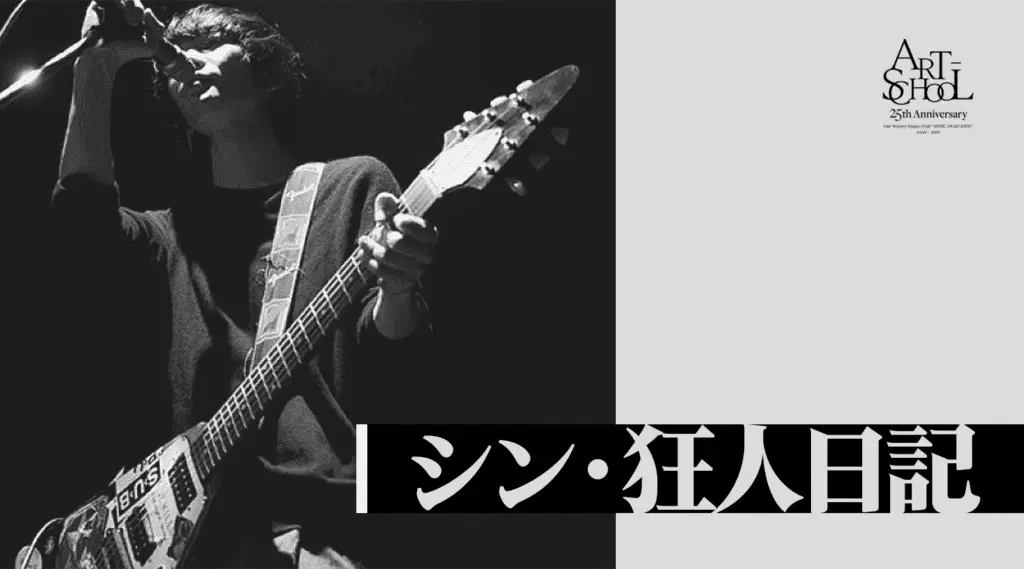来年、上野の森美術館で大ゴッホ展が開催されるというニュースを聞いて、そういえば昔、ゴッホについて詳しく書いた文章をメモに残していたことを思い出して、探してその文章を読んでいた。改めて読んでみるとなかなかに熱量のこもった文章だったので、此処に残したいと思う。読んで頂けたら嬉しいです。
色々な画家が、沢山居ますがその時々の気分で好きな絵や画家が変わるのが、人間の性であり、しかし僕が生涯を通じて考え続けるだろう画家の一人に、ゴッホという画家がいる。ゴッホの描いたアルル星降る夜という絵が、僕は小さな頃から好きだったのだけれど、より深く理解するようになったのは、ゴッホの書簡集を読んでからだった。ゴッホは生涯を通じてたった一枚の絵しか売れなかった。そもそもゴッホが画家を目指したのも、27歳の時だ。しかしそれからの10年間、自殺を計るまで彼は絵を絶え間なく描き続けた。画商であった弟のテオが、全ての生活費と画材を工面し、その代わりにゴッホは無償で描いた絵をテオに送り続けた。彼らはまるでシャム双生児の様に固い絆と信頼で結ばれていたのだ。しかしテオが妻と子供を持ち、ゴッホへの仕送りの金額がやむおえず少なくなり始めてから、ゴッホは自らを追いつめ始めていった。 その辺の事実は後に触れよう。
ゴッホの書簡集を初めて読んだ時に、まず驚かされたのはゴッホ自身の持つ、鋭い批評力と明晰さ、冷静さであった。彼は共に共同生活をしていた画家ゴーギャンとの決別で耳を切り落とした後も、或いはサンレミの精神病院に入院してた時も、全く狂ってはいなく、むしろ自分の「その様な」精神状態を鋭く理解し、観察していた。自らピストルを腹部に撃った最後の日に持ってた手紙の内容でさえも、全くもって「一字も」狂ってはいない。逆に書くと、ゴッホは最後まで「狂えなかった」。だからこそ、殆ど神話の様に悲劇的なゴッホの書簡集が、この殆ど弟に宛てた手紙が意味を大きな意味を持つのである。
ゴッホの絵の時代は、大きく分けてオランダ〜アルル〜サンレミ〜それから最後のオーヴェルシュールの時代まである。僕はなるべくゴッホの文献は集め、展覧会が東京で行われる時には行って、絵も観る様にしていたので、ある程度までは絵の印象を書けると思う。ミレーや、ドラクロアからの影響が強かった時代から、アルル時代、印象派の時代背景もあるのだろうが、彼の色彩感覚は大きく成長して開花し、驚く程美しく繊細な絵をこの時代に何枚も残している。そして個人的には「画家としての」ゴッホのピークはこの時代にあったのだと思う。初めての大きな発作を起こして、それから後の、いわゆるサンレミ時代からの絵は。。僕は、この時代のゴッホの絵を展覧会で実際に観て、メモを取っていたのだが、、一つの魂である。緊張や不安、絶望の影が絵の中にありながら、ギリギリの部分で調和を保っている。言葉にするといかにも陳腐だが、そうとしか思えなかった。ただ、、サンレミの精神病院時代から、最後までのゴッホの絵を本当に「絵」というのか、これは一つの魂じゃないか。一つの糸が切れる様な、その音がはっきりと聞こえているじゃないか。
最後まで気が狂えなかったゴッホ、それから兄の死の一年後には発狂して死んでしまった弟のテオ、二人の墓はいまは隣同士に並べられている。花言葉の「離れると死んでしまう」という言葉の花々に覆われて。
今は、世界中の人が貴方の絵を愛してるんだよって伝えたかった。
愛を込めて